-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年4月 日 月 火 水 木 金 土 « 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
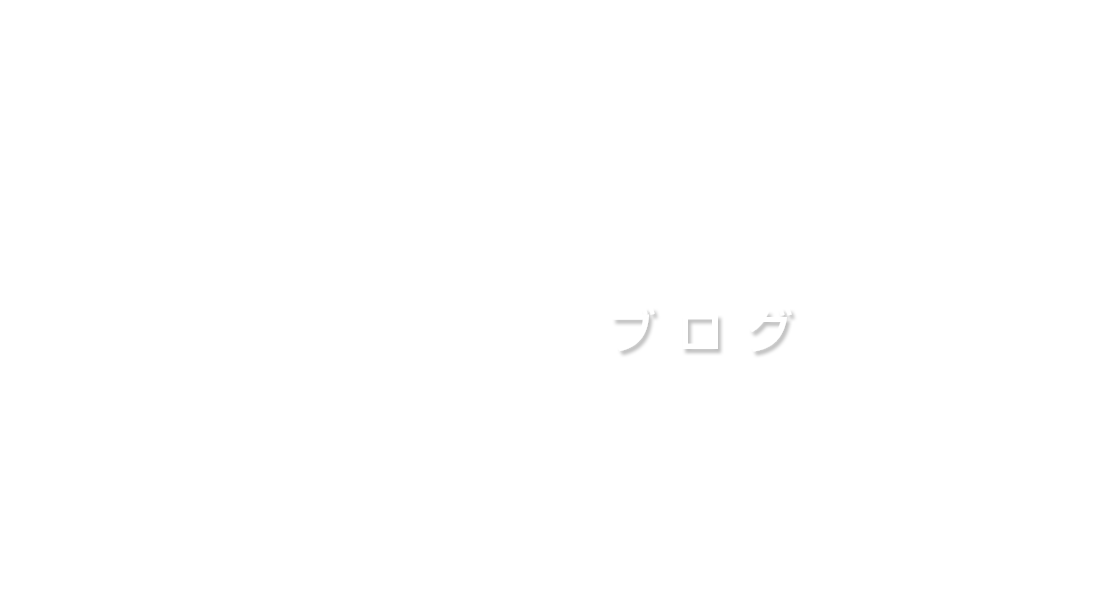
みなさん、こんにちは。
いよいよ春にさしかかるこの季節、まだまだ寒い日もありますが、いかがお過ごしでしょうか。春を彩る桜の花が、そろそろそのつぼみを開こうとしています。
ちなみに、例年ある「桜の開花予想」はどのように行われるかご存知ですか?諸説ありますが、有名なのは「桜の開花600℃の法則」でしょう。2月1日を起点として、毎日の最高気温が600℃になったら桜は開花するという説です。
これを使えば、ある程度自分でも開花予想がたてられそうですね。地域によって何℃かの差は変わってくるようですが、桜の開花には気温が重要のようです。日本を代表する花である桜が綺麗に開花するのを、毎日楽しみにしながら仕事に励むのも良いかもしれません。
さて、桜の花が咲くころといえば、卒園式・卒業式の時期ですね!
この春に学校を卒業した方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご卒業おめでとうございます。ご卒業後、進路にはさまざまな選択肢がありますが、その一つに「働く」ということがあると思います。みなさんは、働くということにどんなイメージを持っていますか?
「大変そう……」「やりがいのある作業」「お金を稼ぐ手段」など、さまざまな印象があることでしょう。実際、働くことは大変であり、お金を稼ぐ手段としてその作業を淡々とこなしている人も多いと思います。
しかしその一方で、自らの仕事にやりがいを感じて、明るい気持ちで仕事をしている人も多いことでしょう。せっかく仕事をするのであれば、より楽しく、より精力的になれるような職を探せるといいですね!
それには、職種だけでなく、職場の環境も見る必要があります。どんなに自分の好きな仕事であっても、同僚や上司との関係が悪ければ、苦痛を伴う職場になってしまう可能性があるからです。
その見極めは難しいですが、今こうしてみなさんが弊社のブログ記事を読んでくださっているように、ホームページや求人サイトから、ある程度推察することはできます。自分に合った職場をみなさんが見つけられるよう祈っています♪
弊社では、一緒に仕事をするお互いのことを仲間だと思っており、休憩時間にはお互いのことを話すこともあります。もちろん、プライベートなことを無理に詮索するといったことはありません。親しみやすい仲間たちと話して距離を縮め、楽しい職場環境を作りながら、自分の仕事に精を出してみませんか?
現在、弊社では求人を募集しております!お気軽にお問い合わせください。
心よりお待ちしております(*^^)v
みなさん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか?
全国的に暖冬の傾向である今年の冬ですが、局所的に大雪が降っている地域もありま
すね。積雪による地面の凍結はスリップしやすく、転んで怪我をしてしまうこともあ
るため、該当地域にお住まいの方は十分に気を付けてください。
さて、2024年は、4年に一度訪れるうるう年。
うるう年に増えた2月29日を「うるう日」といいます。なんとなく、うるう年の2月は
テンションが上がる人もいるのではないでしょうか?カレンダーに印字された2月29
日の文字はいつも新鮮な気持ちを与えてくれますね♪
では、なぜうるう日と呼ばれる2月29日は必要なのか、ご存知でしょうか?
太陽の周りを地球が一周する期間が一年であるため、一年は365日で定められていま
すが、実はピッタリ365日ではなく、365.24日で一周するといわれています。一年で
約6時間ずつ増えていく時間を調整するために、4年に一度、2月29日という一日を足
しています。6時間×4年分の24時間(1日)がうるう日、となるわけです。
うるう年は、紀元前46年にローマのユリウス・カエサルによって制定され、翌年1月1
日から実施されました。では、なぜ2月にうるう日が設けられたのかというと、当
時、古代ローマでは、一年の始まりが春の3月からだと考えられていたからです。2月
は一年で最後の年であり、そのために普段は2月28日までと日数が少なく、うるう日
もそこに付け加えられることになりました。2月が元々少なかった理由も、うるう日
が2月に追加された理由も、古代ローマの歴史に因るものだったのですね♪
ちなみに、ちょっとした豆知識ですが、うるう日(2月29日)生まれの人はいつ誕生日
を迎えるか、知っていますか?「2月29日に生まれた人は4年に一度だけ歳をとる?」
……なんてことは勿論なく(笑)、2月28日の24時をもって、年を重ねるという形に
なっています。気持ち的には前日のお祝いですかね。うるう年でない年は、2月28日
か3月1日のどちらかで、誕生日祝いをすることが多いようです。これは、年齢計算に
関する法律によって一律決められているようです。
毎年きちんとお祝いできるとはいえ、やはりうるう日生まれの人たちにとっては、4
年に一度のうるう年はきっと特別なものでしょう。もし身近にうるう日生まれの方が
いらっしゃる場合は、ぜひ盛大にお祝いしてあげてくださいね(*^^)v
4年に一度のうるう年、せっかくなので今回はそんなうるう年の豆知識をご紹介して
きました。いつもと違う特別感にワクワクしながら、今年の冬も食や遊びを楽しんだ
り、仕事に精を出したり、思い思いの毎日を過ごしてくださいね!
みなさん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか?
全国的に暖冬の傾向である今年の冬ですが、局所的に大雪が降っている地域もありますね。積雪による地面の凍結はスリップしやすく、転んで怪我をしてしまうこともあるため、該当地域にお住まいの方は十分に気を付けてください。
さて、2024年は、4年に一度訪れるうるう年。
うるう年に増えた2月29日を「うるう日」といいます。なんとなく、うるう年の2月はテンションが上がる人もいるのではないでしょうか?カレンダーに印字された2月29日の文字はいつも新鮮な気持ちを与えてくれますね♪
では、なぜうるう日と呼ばれる2月29日は必要なのか、ご存知でしょうか?
太陽の周りを地球が一周する期間が一年であるため、一年は365日で定められていますが、実はピッタリ365日ではなく、365.24日で一周するといわれています。一年で約6時間ずつ増えていく時間を調整するために、4年に一度、2月29日という一日を足しています。6時間×4年分の24時間(1日)がうるう日、となるわけです。
うるう年は、紀元前46年にローマのユリウス・カエサルによって制定され、翌年1月1日から実施されました。では、なぜ2月にうるう日が設けられたのかというと、当時、古代ローマでは、一年の始まりが春の3月からだと考えられていたからです。2月は一年で最後の年であり、そのために普段は2月28日までと日数が少なく、うるう日もそこに付け加えられることになりました。2月が元々少なかった理由も、うるう日が2月に追加された理由も、古代ローマの歴史に因るものだったのですね♪
ちなみに、ちょっとした豆知識ですが、うるう日(2月29日)生まれの人はいつ誕生日を迎えるか、知っていますか?「2月29日に生まれた人は4年に一度だけ歳をとる?」……なんてことは勿論なく(笑)、2月28日の24時をもって、年を重ねるという形になっています。気持ち的には前日のお祝いですかね。うるう年でない年は、2月28日か3月1日のどちらかで、誕生日祝いをすることが多いようです。これは、年齢計算に関する法律によって一律決められているようです。
毎年きちんとお祝いできるとはいえ、やはりうるう日生まれの人たちにとっては、4年に一度のうるう年はきっと特別なものでしょう。もし身近にうるう日生まれの方がいらっしゃる場合は、ぜひ盛大にお祝いしてあげてくださいね(*^^)v
4年に一度のうるう年、せっかくなので今回はそんなうるう年の豆知識をご紹介してきました。いつもと違う特別感にワクワクしながら、今年の冬も食や遊びを楽しんだり、仕事に精を出したり、思い思いの毎日を過ごしてくださいね!
明けましておめでとうございます。
旧年中は格別なご高配を賜り誠にありがとうございました。 本年もより一層サービ
スの向上に努めて参ります。ご支援、お引立てを賜りますようよろしくお願い申し上
げます。
2024年は辰年ですね。
みなさんも知っての通り、十二支には、それぞれ単漢字が当てられています。
子(ね)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う)、辰(たつ)、巳(み)、午(うま)、未(ひつじ)、
申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(い)。
これらは全て動物を表していますが、普段使う漢字とは違いますよね。
辰は「振るう」という文字に由来しており、自然万物が振動し、草木が成長して活力
が旺盛になる状態を表します。
辰は竜(龍)のことでもあり、十二支の中で唯一の空想上の生きものです。 東洋で
権力・隆盛の象徴として親しまれていた龍は、身近な存在であったことから干支に選
ばれたと言われています。
では、ここでクイズです!
「辰」は古代中国では「時間の神」を象徴していた
〇か×か、どちらでしょう?
↓
答えは「×」です。
「辰」は「時間の神」を象徴していたわけではありません。
「辰」は時間や方角を示す暦の単位として使用されていました。古代中国では、辰の
時間は朝の7時から9時までを指し、辰の方角は東南を表します。
辰年は変化と成長を象徴する年とされています。龍のような力強さや威厳を持ちなが
ら、新しい始まりやチャンスに満ちた年と言われています。
この年は、新しい挑戦を始め、大胆な一歩を踏み出すのに最適な時期です。辰年は変
化に富み、飛躍的な成長が期待できる年と言えるでしょう。
また、辰年は人間関係においても良い変化が期待される年です。新しい出会いや、人
とのつながりが深まる機会が増えることでしょう。
辰年の持つ力強さと勇気を借りて、自分自身をステップアップさせる一年にしてみて
はいかがでしょうか。
皆さんが健やかで笑顔溢れる一年になることを社員一同で願っております。
本年もよろしくお願いいたします。
突然ですが、
12月といえば、クリスマス!
――と思い浮かべる方は多いと思いますが、それでは12月23日は何の日かご存知で
しょうか…?
改めまして、みなさんこんにちは。
急に冷え込む日が増え、いよいよ本格的な冬の訪れを感じられる頃になりました。慌
ててコート類を用意した方も多いかもしれません。衣類だけでなく、身体を芯から温
めてくれるお野菜なども身体に取り込んで、風邪をひかないように気を付けてくださ
いね。
さて、みなさんは12月23日といえば何の日かご存知でしょうか?
クリスマスツリーよりもずいぶんと高い、あのタワーの完成日です・・・
そう、333mの高さを誇る「東京タワー」の完工式が執り行われた日となっています!
東京タワーの設計は「塔博士」とも称される、日本の塔設計の第一人者である構造
家・内藤多仲らによって行われ、総工費は約30億円、完成までに約1年半の歳月がか
かったといわれています。
では、そんな膨大な金額や時間をかけてまで、なぜ東京タワーは作られたのでしょ
う?
1953年には NHK が日本初となるテレビ本放送に成功し、その後次々と地方の放送局
が電波を発信できるようになります。しかし、その時には電波塔というものが存在し
なかったため、各局は独自のアンテナを使い電波を発信していました。各局がそれぞ
れ電波を飛ばすのは効率が悪く品質の良いものではありませんでした。
当時日本は高度経済成長期。「全てをまかなう電波塔を作ろう!」という理想の元、
日本一高い建築物を目指して東京タワーが作られたそうです。
今では日本の立派な観光名所として名高い東京タワーですが、実はそのような発想で
実用的な背景に基づいて作られたのだと思うとなんだか感慨深いですね。東京タワー
のおかげで、私たちはテレビを自由に楽しめているといっても過言ではありません
(?)
12月23日は東京タワーの日。
もしまだ登ったことがない方は、この機会に一度登ってみるのもオススメです。地上
約150mにある、メインデッキの大展望台では、東京の景色を一望することができます
よ♪この時期は寒くておうちにこもりがちですが、たまにはお出かけしてみるのもい
いかもしれません(´艸`*)
風邪をひかないようにコートなどを着込んで、おしゃれをして、冬のお出かけを楽し
んでください!
みなさん、こんにちは!
急に冷え込む日が増えてきて、ストーブをつけたりこたつを取り出したりし始めてい
るご家庭も多いのではないでしょうか?季節の変わり目は自律神経が乱れやすく、体
調を崩しやすいので、しっかり身体を温めて風邪をひかないようにしてくださいね。
ところで、11月23日は「勤労感謝の日」ですね。
「勤労感謝の日」というと、働いている誰かに対して何か感謝の意を込めて贈り物を
するイメージがあるかもしれませんが、実は「勤労をたっとび、生産を祝い、国民た
がいに感謝しあう日」として、“国民の祝日”に制定されています。 つまり、仕事
仲間同士でお互いに感謝し合ったり、自分自身の働きに対しても「よくやった」と褒
めたりするための祝日なのです。この機会に、自分の働きを振り返ってみませんか?
「働く」ということは、誰もが簡単にできることではありません。社会人になると、
急に「働く」という場に駆り出されますが、学校の試験などと違ってゴールがなく、
戸惑うこともおおいにあります。その中でも、自分で決めた小さなゴールをいくつも
達成していくという、コツコツとした積み重ねが、やがて私たちを一人前の社会人と
して形成していきます。
しかしながら、自分で目標を決めて、その目標のために頑張るのはとても難しいこと
です。一人で達成するのが難しいからこそ、同僚や上司、そして部下と助け合いなが
ら、私たちは仕事をしていきます。だからこそ、「働く仲間」をお互いに敬い合い、
感謝し合える「勤労感謝の日」は、大切な一日だといえるでしょう。
「勤労感謝の日」は、ただの祝日ではなく、「働く」ことを頑張っている、頑張ろう
としているみなさんが称えられるべき祝日なのです。好きな食べ物を食べるも良し、
趣味を一日楽しむも良し、自分の頑張りをたくさん褒めてあげてくださいね。そして
できれば、一緒に働いている仲間や、職場は違くとも頑張っている家族や友人にも、
感謝の意を述べられるといいですね。
さて、ここまで読んでくださった、「働く」場所や仲間を探しているみなさん、せっ
かく汗水たらして働くのであれば、お互いの能力、人柄、仕事ぶりを尊敬し合える職
場を選びませんか?
当社では、私たちとともに、一生懸命働いてくださる方を募集しております。お気軽
にお問い合わせください(*^^)v
心よりお待ち申し上げております!
みなさん、こんにちは!
本格的に秋の風が吹き始め、「〇〇の秋」をたくさん楽しめる季節となってきまし
た。
例えば食欲の秋。栗ご飯や秋刀魚の塩焼き、松茸のお吸い物など、この時期食べたい
ものは多く、食べ過ぎてしまうこともしばしば。ほかにも読書の秋、芸術の秋など、
秋にやりたいことはたくさんです。
さて、10月の第2月曜日は何の日かご存知でしょうか?答えは「スポーツの日」で
す。元々の名称は「体育の日」でしたが、2020年に「スポーツの日」と名前が変えら
れました。
なぜ10月の第2月曜日が「スポーツの日」かというと、1964年の10月10日に、東京で
オリンピックが開催されたことを記念して制定された国民の祝日だからだそうです。
「国民がスポーツに親しみ、健康な心身を培う日」とされており、この3連休を使っ
て運動会を開催している学校も数多くあります。2000年の法改正により、10月の第2
月曜日を国民の祝日「スポーツの日」として制定されているため、3連休が嬉しい方
も多いのではないでしょうか?
そうそう、冒頭で触れた「〇〇の秋」の一つに「スポーツの秋」というのもあります
よね。運動会以外にも、この季節にはスポーツ系のイベントが増えていたり、レ
ジャー施設に人がたくさん集まったりと、スポーツの秋を連想させる出来事がいっぱ
いです。
これには、湿気や気温がちょうど過ごしやすい季節になり、運動に励みやすいという
理由があると思いますが、それは肉体労働でも同じことがいえます。仕事がしやすい
この季節、ぜひ私たちと一緒に労働しませんか?健康な身体作りにも繋がりますし、
もし今あなたが新しい仕事を探しているのであれば、働きやすい今の時期がチャンス
です!
食欲の秋に釣られて食べ過ぎてしまった身体をキッチリ締めるきっかけにもなります
(笑)美味しい物を食べて、あくせく働き、しっかりと睡眠をとる……、そんな素敵な
「秋」を、弊社の仲間たちとともに過ごしてみませんか?仕事の終わりには秋の味覚
を一緒に楽しむのも良いですね。あなたがオススメする「〇〇の秋」をぜひ聞かせて
ください♪
弊社では現在、みなさまからの求人を募集しています。
求人募集ページよりご連絡いただければ幸いです(*´ω`*)
社員一同、心よりお待ちしております!
夏が終わり始め、少しずつ秋の風が吹いてくる頃になってきましたが、みなさまいか
がお過ごしでしょうか。
さて、突然ですが、9月18日は何の日かご存知ですか?
そう、「敬老の日」です!
敬老の日は、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日とし
て、国民の祝日に定められています。自分のおじいちゃんやおばあちゃんだけでな
く、ご両親や、学生時代の恩師など、これまでの人生でお世話になった方々へ感謝を
伝える大切な日です。
せっかくならご自身で稼いだお金で、感謝を伝えたいあの人へ、何かプレゼントをし
てみませんか?
高価なプレゼントである必要はありません。大切な人を想いながら働き、稼いだお金
で贈り物をすることが、感謝の気持ちになることと思います。
感謝を伝える方法は、もちろんプレゼントだけではありません。遠方に住んでいる方
にはなかなか会うことは難しいですし、一緒に住んでいるご両親にプレゼントを急に
渡すのも照れくさい気持ちがあるかもしれません。それぞれの事情の中で、お手紙を
渡したり、どこかへ一緒に出掛けたり、人それぞれ感謝の伝え方はあるかと思いま
す。
ですが、一生懸命働いたお金でプレゼントした「感謝」は、きっとあなたの大切な人
へ届き、かけがえのない思い出として心に残ることでしょう。そしてあなた自身に
も、その経験は人生の中でかけがえのない宝物として刻まれていくに違いありませ
ん。
誰かのために仕事をする、というのは気持ちの良いものです。仕事をするのに、辛
い、嫌だ、やりたくない、といったマイナスな気持ちをわざわざ抱える必要はありま
せん。そして、せっかく頑張って働くのですから、なにか目標があったほうがやりが
いもあるかと思います。やりがいのある仕事で稼いだお金で、感謝を伝えられたらそ
れほど良いことはありません。
仲間とともに一生懸命働きながら、先輩や同僚とプレゼントの相談をするのも良いか
もしれません。1年に1回しかない「敬老の日」だからこそ、特別なプレゼントをして
みたいものです。どんなプレゼントが良いか、休憩時間に話しながら、そのプレゼン
トのためにお金を稼ぐ時間は、かけがえのない時間になることでしょう(´艸`*)
弊社では現在、みなさまからの求人を募集しています!
ぜひ、求人募集ページより、ご連絡ください(*´ω`*)
社員一同、心よりお待ちしております。
「職人の心得」について考えてみました。
職人とは、その道のプロフェッショナルであり、技術や知識を磨き上げ、日々の仕事
に誇りを持ちながら取り組む方々を指します。どの分野においても「職人の心得」は
とても重要だと思います。
いろいろな考え方があると思います。ひとつの考え方としてお読みいただけると幸い
です。
まず職人が心得るべきは「技術の継承と向上」だと思います。
職人は、その分野の技術やノウハウを学び、その技術を継承していく役割を担いま
す。古くからの伝統的な技術や工程を守りながら、新しいアイデアや技術革新を取り
入れることで、進化し続ける必要があります。技術は時代と共に変化しますが、その
変化に適応し、自分自身のスキルを高めていく姿勢が大切です。
職人には「誇りと責任」が欠かせません。
自分が生み出すものや提供するサービスに誇りを持ち、それを通じてお客様に満足と
喜びを提供することが使命です。何事も最善を尽くし、納得のいく仕事をすること
で、自己満足だけでなく、周囲の人々にも良い影響を与えることができます。そのた
めには、納期や品質に対する責任感を持ち、信頼を築くことが大切です。
「謙虚さと向上心」も欠かせません。
自分の技術や知識を高めることは一生の課題です。自分が十分に優れていると思って
しまうと、成長のチャンスを逃してしまうこともあります。謙虚な姿勢で周りの人々
から学び、向上心を持ち続けることで、より高みを目指すことが可能です。
最後に「人との繋がり」を大切にすることも他の心得と並んで重要です。
職人は単なる技術の提供者ではなく、人々とのコミュニケーションを通じて、信頼関
係を築きます。お客様のニーズを理解し、それに応えるためにコミュニケーション能
力を磨くことで、お客様との長い関係を築くことができます。
目の前の仕事に全力を注ぎ込み、誇りを持って成果を出すこと。新しいことにチャレ
ンジする姿勢を大切にし、向上心を持ち続けること。そして、人々との良好なコミュ
ニケーションを通じて信頼関係を築くこと。これらの要素は「職人の心得」と私たち
の日常に共通する価値です。
職人の心得は、技術だけでなく、心の在り方や倫理観を含んでいます。就いている仕
事が「職人」と呼ばれるジャンルでなかったとしても、日々の仕事や生活の中で役に
立つと思います。
もしあなたが仕事を通して「職人の心得」を体得して持続的に成長したいと思ってい
るなら、私達がその環境を用意できるかもしれません。
最高の環境をご用意してお待ちしています!
仕事を行う上で大切なことはたくさんありますが、特に若い求職者の皆さんが仕事を
通して持続的に成長するために重要だと思うポイントをまとめてみました。
1.自己啓発を続けること
技術や知識は日々進歩しています。常に学び続け、自己成長に努めることが重要で
す。新しいスキルを習得し、業界のトレンドや最新の情報に敏感になりましょう。勉
強会やセミナーに参加したり、オンラインの学習プラットフォームを利用するなど、
自己啓発の機会を積極的に探しましょう。
2.コミュニケーション能力の向上
コミュニケーションは仕事のすべての面で重要です。相手と良好な関係を築くために
は、明確かつ効果的に自分の考えや意見を伝えることが必要です。また、相手の意見
を尊重し、協力し合うことも大切です。コミュニケーション能力を高めるために、プ
レゼンテーションスキルやネットワーキングの方法を学ぶと良いでしょう。
3.チームワークの重要性を理解すること
多くの仕事はチームで行われます。他のメンバーとの協力や協調性が求められます。
自分の意見を主張することも大切ですが、チームの目標達成のためには柔軟性や協力
も必要です。チームプレイの経験を積むために、大学のクラブ活動やボランティア活
動に積極的に参加することをおすすめします。
4.プロフェッショナリズムを意識すること
仕事ではプロフェッショナリズムが求められます。時間厳守や約束の守り方、ルール
や規則への遵守など、ビジネス環境でのマナーや倫理に気を配ることが重要です。ま
た、自分の仕事に対して責任を持ち、最善の結果を追求する姿勢を持つことも大切で
す。
5.ポジティブなマインドセットを持つこと
仕事には挑戦や困難もつきものですが、それを前向きに捉えることが重要です。失敗
や挫折から学び、成長するチャンスと考えることが大切です。ポジティブな姿勢で取
り組むことで、自身のパフォーマンスやモチベーションを高めることができます。
これらの要点はあくまで一部ですが、若い求職者の皆さんにとって仕事で成功するた
めの基本的なガイドラインといえると思います。自己啓発やコミュニケーション能
力、チームワーク、プロフェッショナリズム、ポジティブなマインドセットを意識
し、持続的な成長を目指してください。
もしあなたが仕事を通して持続的に成長したいと思っているなら、私達がその環境を
用意できるかもしれません。
最高の環境をご用意してお待ちしています!