-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年4月 日 月 火 水 木 金 土 « 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
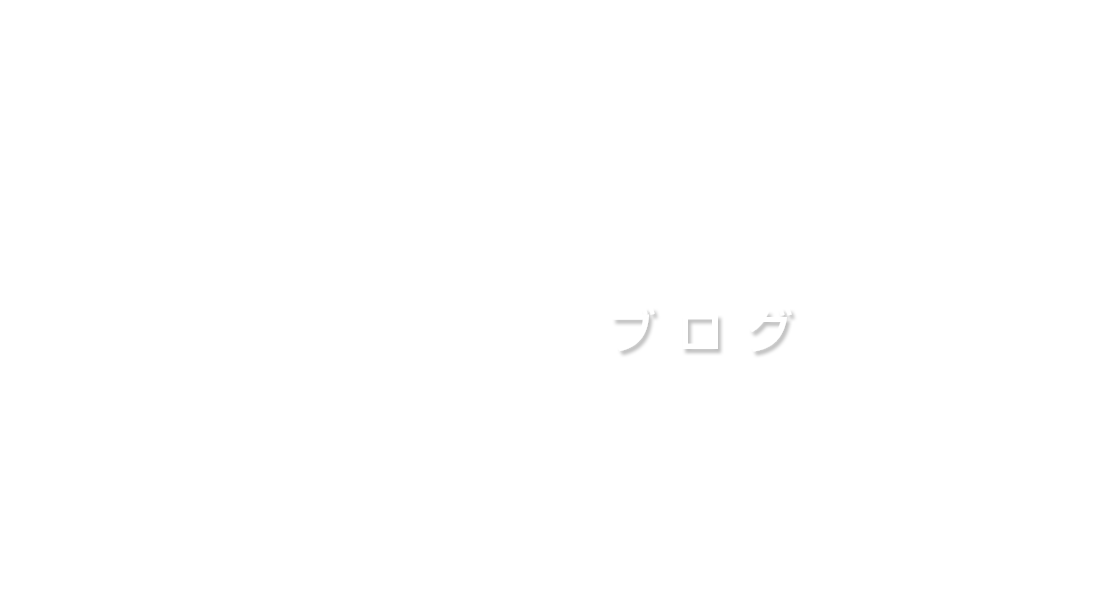
みなさん、こんにちは!
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますね(^o^)丿
年が明けると、さまざまな伝統行事が待っていますよね。どれも由緒ある行事なのですが、ただ何となく参加しているという方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、お正月の伝統行事について、その意味や由来をご紹介していきます!
まずは、初詣からスタート!初詣は、その年の無事と幸せを願って神様にご挨拶に行く大切な行事です。多くの方が元日に行かれると思いますが、実は1月1日~1月7日までが松の内と呼ばれる期間。この間であれば、いつ行っても「初詣」になるんですよ。混雑を避けて、2日以降に行くのもおすすめです。
初詣の参拝方法も、きちんと押さえておきたいポイントです。鳥居をくぐる前に一礼、参道は端を歩き、中央は神様の通り道。手水舎での清め方は、左手で柄杓を持ち、右手を清め、次に右手で柄杓を持ち直して左手を清めます。その後、左手に水を受けて口を清め(飲んだ水は飲み込まず脇に吐き出します)、最後に柄杓を立てて柄を清めます。
次は初日の出!新年を告げる朝日を拝むことには、太陽神である天照大御神を敬う意味が込められています。最近では、初日の出クルーズやスカイツリーなどの展望台での観賞も人気ですね。ご自宅のベランダや近所の高台でも、ゆっくり朝日を拝むことができますよ。気象庁のウェブサイトで日の出時刻を確認して、少し早めに目的地に到着するのがおすすめです(*^^*)
そしてお待ちかねのおせち料理!黒豆は「まめに暮らせますように」、数の子は「子孫繁栄」など、一つ一つの料理に縁起の良い意味が込められています。田作りは五穀豊穣、昆布巻きは「喜び」を表すなど、実は知らない意味がたくさん。最近では、和洋折衷のおせちや、一人用のミニおせち、オードブル形式のパーティーおせちなど、ライフスタイルに合わせた楽しみ方も増えてきましたね。
伝統的なおせちを全て手作りするのは大変ですが、一品だけでも作ってみるのはいかがでしょうか?黒豆や煮しめなど、基本の作り方を覚えておくと、普段のお料理の幅も広がりますよ。
最後は1月7日の七草粥です。お正月のごちそうで疲れた胃腸を休めるという実用的な意味と、春の七草を食べて無病息災を願う意味があります。七草は「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」。スーパーでも七草セットが売られているので、ぜひチャレンジしてみてくださいね!七草粥を食べながら、「唐土の鳥が日本の正月に、渡らぬ先に、七草なずな」と唱えるのも粋な楽しみ方です(^-^)
お正月の伝統行事には、先人たちの知恵と願いが詰まっています。形を変えながらも、大切に受け継がれてきた行事を、現代の暮らしに合わせて楽しんでいきましょう!
お正月の行事を楽しんだ後は、気持ちを新たにこれからの1年の過ごし方に想いを馳せてみてはいかがでしょうか。そのために私たちは快適な時間を提供できればと思います。
良い計画を思いついたら私たちにも教えてください!お会いできるのを楽しみにしています^^
本年もどうぞよろしくお願いいたします。